Steenrod 篇:§12. Steenrod 代数の双対
この節では、古典論と同様に、motivic Steenrod algebra \( A^{*,*}\) の双対 \( A_{*,*}\) を定義し、古典論と並行な性質を証明しています。今日も係数は \( \mathbf{Z}/2\) とします。
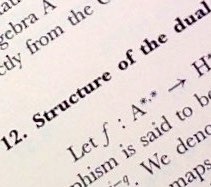
古典論では、Steenrod algebra \( A^* \) の双対 \( A_* \) は、p 次部分として \( A^p \) の線型双対 \( \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}/2}(A^p,\mathbf{Z}/2) \) を持つような次数付きベクトル空間として定義するのでした。 \[ \begin{array}{cccc} &\cdots A^0 \cdots &A^p &\cdots \\ &&\swarrow A_p\text{ の元}& \\ &\mathbf{Z}/2 &&\end{array}\tag{古典論}\] \( \mathbf{Z}/2\) を、点のコホモロジー環 \( H^*(pt)\) と解釈しましょう。すると、\( A_p \) は、次数付き線型写像の記号 \( \mathrm{Hom}^{*}_{\mathbf{Z}/2} \)を用いて次のように書けます:\[
A_p := \mathrm{Hom}^{-p}_{\mathbf{Z}/2} (A^*, H^*(k))
\] これがモチビックな場合にはどのように翻訳されるか見ていきましょう。
定義と加群構造
モチビックな文脈では、ここでのターゲット \( \mathbf{Z}/2 \) は点のコホモロジー群 \( H^{*,*}(k) \) に取って代わられます。\( \mathbf{Z}2 \)-線型写像という条件は、左 \( H^{*,*}(k)\)-線型という条件で代替します。 \[ \begin{array}{cccc} &\cdots A^{0,0} \cdots &A^{p,q} &\cdots \\ \swarrow & &\swarrow A_{p,q}\text{ の元}&\swarrow \\ \dots &H^{0,0}(k) &\dots & H^{p,q}(k) \end{array} \tag{motivic}\] すなわち、数式で書いた定義は \[ A_{p,q}:= \mathrm{Hom}^{-p,-q}_{H^{*,*}(k)}(A^{*,*},H^{*,*}(k)) \] とでもなります。だだし、\( \mathrm{Hom}^{-p,-q}_{H^{*,*}(k)} \) という記号で次数 ( -p,-q ) の線型写像 \( \bigoplus _{i,j}A^{i,j}\to \bigoplus _{i,j}H^{i,j}(k) \) の集合を表しました。
定義からただちに、\( A_{*,*}\) には \( H^{*,*}(k) \) の右 \( H^{*,*}(k)\)-加群構造からくる右 \( H^{*,*}(k)\)-加群構造があり、双線型写像 \[ A_{p,q}\otimes _{H^{*,*}(k)} \bigoplus _{i,j} A^{i+p,j+q} \to\bigoplus _{i,j} H^{i,j}(k) \] があることになります。
一方、\( A^{*,*} \) 上の右 \( H^{*,*}(k) \)-加群構造の pre-composition により、 \( A^{*,*} \) には左 \( H^{*,*}(k)\)-加群構造があります (pre-composition なので左右が逆になりました。たとえば、\( u\in H^{a,b}(k), v\in H^{c,d}(k)\) と \( \psi \in A_{p,q} \) に対して、\(uvψ\) は写像 \[ A^{*,*}\xrightarrow{(-)\cdot u }A^{*+a,*+b}\xrightarrow{(-)\cdot v }A^{*+a+c,*+b+d}\xrightarrow{ψ}H^{*+a+c-p,*+b+d-q}(k) \] で計算できます)。Voevodsky (p.48) はこの辺りをイイカゲンに書いている気がしてならないのですが、\( H^{*,*}(k) \) は可換環 (奇素数係数でも次数可換) なので、ここで余計に悩むのは一旦避けで、先に進みたいと思います。
環構造
Steenrod 代数は余積構造 \( A^{*,*}\to A^{*,*}\otimes _{H^{*,*}(k)} A^{*,*} \) を持ちましたので、\( A_{*,*}\) は双対的に積構造を持ちます: \[ A_{*,*}\times A_{*,*} \to A_{*,*} ,\] 念のため、この写像がどう定まっているか丁寧に確認しましょう。元 \( \phi \in A_{p,q},\phi '\in A_{p',q'}\) の積 \( \phi \cdot \phi '\in A_{p+p',q+q'} \) は次の線型写像として定義します: \[ \begin{array}{rl}A^{i,j}\xrightarrow{余積} (A^{*,*}\otimes_{H^{*,*}(k)}A^{*,*})^{i,j} & \xrightarrow{\phi \otimes \phi '}(H^{*,*}(k)\otimes _{H^{*,*}(k)}H^{*,*}(k))^{i-p-p',j-q-q'} \\ & \xrightarrow[\cong ]{積} H^{i-p-p',j-q-q'}(k) . \end{array}\] ここで途中の写像 \( \phi \otimes \phi ' \) が well-defined であることは、一応、非自明です。表記の写像が、\( A^{*,*}\times A^{*,*} \) 上で両辺の左 \( H^{*,*}(k)\)-加群構造について双線型でなければならないからです。 が、これはちょうど \( \phi ,\phi ' \) が左 \( H^{*,*}(k)\)-線型写像であるという仮定により、問題とならないことがわかります。
\( A^{*,*}\) 上の余積が余結合的・余可換であったことから、\( A_{*,*}\) の積構造は結合的・可換 (!) であることになります。(アプリオリには次数可換だが、今は \( \mathbf{Z}/2\) 係数なので結局、可換)。\( A^{*,*}\) が高度に非可換な環であったことに比べると、この可換性は大きな利点です。せっかくなので命題として際立たせておきましょう:
命題:
\( A_{*,*}\) は上記の積構造により、結合的・(次数) 可換な環である。
双対基底
\( A^{*,*}\) は左 \( H^{*,*}\)-加群として、admissible 単項式からなる自由基底 \( (Sq^I)_{I\text{: admissible}} \) を持ちました (しかも、次数が適切にバラけている)。したがって \( A_{*,*} \) はその双対基底を持ちます。それを \( \theta (I)^*\) と書くことにしています: \[ A_{*,*}=\bigoplus _{I\text{: admissible}} \theta (I)_* \cdot H^{*,*}(k) . \] この基底は環構造に対して次のように振る舞います。\[ \theta (J)_*\cdot \theta (K)_*=\theta (J+K)_*. \] ここで、admissible 添字どうしの和は、両者を右端に揃えて書いた上で、成分ごとに足します。この公式は \( A^{*,*} \) の余積で \( Sq^I \) が \( \sum _{J+K=I} Sq^J\otimes Sq^K \) に写ることの言い換えです。
これだけでもそれなりに \( A_{*,*} \) の構造がわかった感じがしますが、\( A_{*,*}\) の余積構造も含めて見るために、より適した基底があるので、それを導入するための準備が必要です。
トートロジカルな環準同型 \( \lambda \)
次で定義される写像もモチビック特有のものです。任意のスムーズな X に対して:\[ \begin{array}{ccc}\lambda \colon H^{*,*}(X)&\to &H^{*,*}(X)\otimes _{H^{*,*}(k)} A_{*,*}
\\ w &\mapsto & \sum\limits _{I} Sq^I(w)\otimes \theta (I)_* .
\end{array} \] 与えられた w に対して、\( Sq^I(w)\neq 0 \) となる \( I\) は次数(多様体の次元から決まる)の関係から有限個なので、和は有限和です。
この写像は、\( A^{*,*} \) の定義そのものから来るペアリング \[
H^{*,*}(X)\otimes _{H^{*,*}} A^{*,*} \to H^{*,*}(X) \] から出発して、(次数付き) \( \otimes \) と \( \mathrm{Hom}\) の随伴により \[ H^{*,*}(X) \to \mathrm{Hom}_{H^{*,*}(k)}(A^{*,*}, H^{*,*}(X))\xleftarrow[\cong ]{} A_{*,*}\otimes _{H^{*,*}(k)} H^{*,*}(X) \] とすることでも得られます。最後の逆向きの同型は、環上の有限生成射影加群などの文脈でならいつでも成り立つ書き換えです。この場合は \( A^{*,*}\) が \( H^{*,*}(k)\)-加群として自由で、その基底の次数が適切にバラけている (何らかの意味で局所有限) ので有効です。
この λ が環準同型となっていることをちょっと確認したいと思います。(そもそも、右辺に現れているのは可換環の可換環上でのテンソルなので、環構造があることは大丈夫です。)
命題:
λ は環準同型である。
\( w,v\in H^{*,*}(X)\) をふたつの元とします。 \( wv \) という元はまずは \[
\lambda (wv)=\sum _I Sq^I(wv)\otimes \theta (I)_*
\] に写りますが、これが Cartan 公式により分解できるので \[
= \sum _{J+K=I} Sq^J(w)Sq^K (v)\otimes \theta (I)_* \] と計算できます。一方、\[
\lambda (w)\cdot \lambda (v)=\bigl( \sum _{J} Sq^J(w)\otimes \theta (J)_*\bigr) \cdot \bigl( \sum _{K} Sq^K(v)\otimes \theta (K)_*\bigr)
\] です。両者を見比べると、等しいことがわかります。 (Cartan 公式をつごう 2 回使ったので、もしかしたら単なる一般論で証明できることなのかもしれません。)
スムーズな多様体とは限らない空間 X に対しては、和は必ずしも有限にとどまりません。が、いずれにせよ、固定した次数には有限個の項しか現れません。ターゲットを色々な次数についての直積だと思うことで、必要ならば λ の定義を拡張することにしましょう。
基底 \( τ_k\) と \( \xi _k\)
とくに \( X=B\mu _2 \) (ind-smooth スキームで表示しているのでした) の場合を考えたいです。この空間のコホモロジーは次のようになっていました。 \[
\Bigl. {H^{*,*}(k) [ [u,v ] ] } \Bigm/ {u^2=[-1]u+[-1]v} \Bigr.
\] モチベーションはともかくとして、いかにも意味ありげな、次のふたつの元を考えましょう。\[ \begin{array}{rcl}
\lambda (u)&=&\sum\limits _{I\text{: adm}} Sq^I(u)\otimes \theta (I)_* \\
\lambda (v)&=&\sum\limits _{I\text{: adm}} Sq^I(v)\otimes \theta (I)_*
\end{array}\] Admissible 添字のうち、同じ長さのもののうちでは一番小さい \( I=(2^{k},\dots ,2,1)\) の形の添字に対しては \[ Sq^{I}(u)=Sq^{ (2^{k},\dots ,2) }(v)=v^{2^{k }} \] であり、ほかの admissible 添字に対しては次数の関係で \( Sq^I (u)=0 \) です (途中で、自身の次数よりも大きな \( Sq^*\) に出会って 0 になってしまうため)。よって公式 \[
Sq^I(u)=\begin{cases}
v^{2^{k}} & \text{ if } I \text{ has the form }(2^k,\dots ,2,1) \\
0 & \text{ else }
\end{cases}
\] を得ます。\( I\) が empty sequence のときは、\( Sq^I =\mathrm{id}\) なので勿論 \( Sq^I(u)=u\) です。
\( v\) に対しても同様に、\( Sq^1(v)=0 \) という公式を思い出し、次数による消滅も考慮に入れることで公式 \[
Sq^I(v)=\begin{cases}
v^{2^{k}} & \text{ if } I \text{ has the form }(2^k,\dots ,4,2) \\
0 & \text{ else }
\end{cases}
\] を得ます。\( I\) が empty sequence の場合は \( Sq^I(v)=v\) です。まとめると、\( \lambda (u)\), \( \lambda (v)\) は次の級数になります。\[ \begin{array}{ccc}
\lambda (u)&=&u\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{k\ge 0} v^{2^k}\otimes \theta ( ( 2^k,\dots ,1) )_*\\
\lambda (v)&=&v\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{k\ge 1} v^{2^k}\otimes \theta ( ( 2^k,\dots ,2) )_*
\end{array}\] そこで、ここに現れた意味ありげな \( A_{*,*} \) の元に名前をつけます:\[ \begin{array}{ccl}
τ _k &:=& \theta ( (2^k,\dots ,1) )_* \in A_{2^{k+1} -1\ ,\ 2^k -1 } \\
\xi _k&:=& \theta ( (2^k,\dots ,2) )_* \in A_{2^{k +1} -2\ ,\ 2^k -1 } .
\end{array}\] したがって、上の式は\[ \begin{array}{ccc}
\lambda (u)&=&u\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{k\ge 0} v^{2^k}\otimes τ _k\\
\lambda (v)&=&v\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{k\ge 1} v^{2^k}\otimes \xi _k
\end{array}\] ということになります。
ちなみに、Voevodsky の論文は \( τ_k\) と \( \xi _k \) の使い分けについて、一瞬混乱が見られます。p.45 の 2 行目で定義されている \( \xi _i \) と \( τ_i\) はあべこべです(定義式に書いてある \( y_{l^i}\) と \( y'_{l^i}\) があべこべで、次数は合っている)。同じページの式 (12.3) までは、あべこべの定義で話が進行します。その次の (12.4) で、突然定義が入れ替わり、以降は一貫しているようです。
ついでなので、次数がなぜこうなるのか説明しておきましょう。\( τ _k \) の次数を \( p,q\) とでもします。\( v\in H^{2,1}\) なので、\( v^{2^k}\otimes \xi _k \) の次数を計算すると \[ 2^k\cdot (2,1)-(p,q) \] となります。一方、もともとこの項は \( \lambda (u) \) の一部だったので、この次数は \( (1,1) \) であるべきです。したがって \[ \deg (\xi _k)=(p,q)=(2^{k+1}-1,2^k -1) \] とわかります。\(\xi _k\) の方も同じように、一次方程式 \[ 2^k\cdot (2,1)-(p,q)=(2,1) \] から \[ \deg (\xi _k )=(p,q)=(2^{k+1} -2,2^k -1) \] と計算できます。
基底の記述
以下、しばらく、整数の列 \[ I=(\epsilon _0,r_1, \epsilon _1 ,r_2 ,\dots , r_k ,\epsilon _k ) \] で \( \epsilon _j\in \{ 0,1 \} \) かつ \( r_j\ge 0\) を満たすものを考えます。ε と r で下添字の始まり方が違っていて変な感じもしますが、我慢してください。
これらは admissible な添字ではありません。 かといって admissible な添字と関係がないわけではありません。Admissible な添字 \[ I'= (\epsilon _0, i_1,\epsilon _1 ,\dots , i_k,\epsilon _k ) \] に対して、\( r_j\) がその admissible ぐあい \( i_j-(\epsilon _j + 2i_{j+1}) \) を表していると思うと、admissible な \(I' \) と今のような \(I\) が一対一に対応することになります。上記の \( I\) のタイプの添字に対して、プライム \( '\) を付けたもの \( I'\) でもって対応する admissible な添字を表す約束にしましょう。
\(I\) のタイプの添字どうしの大小関係を、\( (1,2,0,\dots )< (0,0,1, \dots , ) \) という風に入れます。つまり、列の右側に 0 を補って無限の長さの列とみなしたうえで、なるべく右側にある成分が大きい方が大きい、と定めるということです。
さて添字 \( I=(\epsilon _0,r_1,\epsilon _1,\dots ,\epsilon _k ) \) に対して、 \( A_{*,*} \) の元 \( \omega (I)\) を \[ \omega (I):= τ _0^{\epsilon _0}\xi _1^{r_1}τ _1^{\epsilon _1}\cdots τ_k ^{\epsilon _k} \] で定めます。もちろん、\( A_{*,*}\) は可換環なので、掛ける順番は変えても構いません。このとき \( A_{*,*}\) の元の族 \( \{ \omega (I) \} _{I} \) と \( A^{*,*}\) の元の族 \( \{ Sq^{I'} \} _{I'\text{: adm}} \) は、ペアリング \( A^{*,*}\times A_{*,*}\to H^{*,*}(k) \) について、次をみたします。
定理 ([Reduced power, Th.12.4]):
上記のような任意 \( I\) に対して、対応する admissible 添字を \( I'\) と書くとき、\[
\langle Sq^{I'} , \omega (I) \rangle =\pm 1 .
\] また、\( I<J \) となる添字の組に対してはつねに \[
\langle Sq^{I'} ,\omega (J) \rangle =0 .
\] とくに、\( \{ \omega (I) \} _{I} \) は \( A_{*,*} \) の \( H^{*,*}(k)\) 上の自由基底をなす。
「とくに」以下の主張が成り立つのはもちろん、ベクトルの族 \( \{ \omega (I) \} _{I} \) を基底 \( \{ \theta (I')_* \} _{I'} \) で表した行列が下三角 \[ \left( \begin{array}{cccc}
1 &0&0& \\
*&\pm 1&0& \\
*&*&\pm 1& \\
\vdots &*&*&\ddots \end{array} \right)
\] となっているからです。定理の主要部の証明は、\( \omega (I) \) の次数に関する帰納法で行うのですが、後日書きたいと思います。(本「Cohomology Operations」では p.137, Milnor の論文では p.160 に載っている。)
さらに、 加群としての基底というだけでなく、次のように環構造もはっきりと決めることができます。下に現れる [ -1] という記号は、\(-1\in k^*\) で代表される \( H^{0,1}=\mu _2(k) \) または \( H^{1,1}=k^*/(k^*)^2 \) の元で、どちらを指すかは次数を数えれば逆算できます。書き分けると却って記憶しづらくなるので、同じ記号を使ってしまっています。
定理 [Reduced power, Th.12.6]:
\( A_{*,*}\) は \( H^{*,*}(k)\)-代数として次の環に同型である。\[
\Bigl. H^{*,*}(k) [ τ_i {(i\ge 0)},\ \xi _i {(i\ge 1)} ] \Bigm/ (τ_i^2=[-1]\xi _{i+1} +[-1]τ _{ι+1}+[-1]τ_0 \xi _{i+1}) . \Bigr. \]
前の定理により、\( A_{*,*} \) の環構造で欠けている情報は \( τ_i^2\) たちの値だけとなっています。\( τ_i \) たちを定義する式 \( \lambda (u)=u\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{i\ge 0} v^{2^i}\otimes τ_i \) の両辺を 2 乗すると (いま \( \mathbf{Z}/2\) 上の可換環なので、各項を 2 乗すればよいです): \[
\lambda (u^2)= u^2\otimes \mathrm{id} +\sum _{i\ge 0} v^{2^{i+1}}\otimes τ_i ^2
\] です。左辺を別の方法で計算して、\( v^{2^i} \) の係数として定理にある式が出てきてくれると嬉しいです。私たちは \( u^2=[-1]u+[-1]v \) ということを知っているので、これを代入すればよいです。ここで、\( u\) にくっついている [ -1] は \( H^{1,1}(k)\) に属していて、\( v\) にくっついている [ -1] は \( H^{0,1}(k)\) の元です。両者の λ による像を知っておく必要があります。次数を区別するために、しばらく \( [ -1]^{0,1}\)、\( [ -1]^{1,1} \) と書き分けましょう。
\( Sq^1\) = Bockstein は \( [ -1]^{0,1}\mapsto [ -1]^{1,1},\ [ -1]^{1,1}\mapsto 0 \) と作用することがチェックできます(cf. \(
\begin{array}{ccccccc}
0\to &\mathbf{Z}&\to &\mathbf{Z}&\to &\mathbf{Z}/2 &\to 0 \\
&\downarrow &&\downarrow && ||& \\
0\to &\mathbf{Z}/2&\to &\mathbf{Z}/4&\to &\mathbf{Z}/2&\to 0
\end{array} \) )。次数的な理由により、両方の [-1] にはそれ以上の \( Sq^*\) は自明に作用しているということがわかります (cf. Lem.9.9)。なので \[ \begin{array}{ccl}
\lambda ([ -1]^{0,1})&=&[ -1]^{0,1}\otimes \mathrm{id} +[ -1]^{1,1}\otimes τ_0 , \\
\lambda ([ -1]^{1,1})&=&[ -1]^{1,1}\otimes \mathrm{id} \end{array}\] です。結果として:\[ \begin{array}{rl}
\lambda (u^2)
= &[-1]^{1,1} \Bigl( u\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{i\ge 0} v^{2^i}\otimes τ_i \Bigr) \\
{} &+ \bigl( [-1]^{0,1}\otimes \mathrm{id}+[ -1]^{1,1}\otimes τ_0 \bigr) \cdot \Bigl( v\otimes \mathrm{id}+\sum\limits _{i\ge 1} v^{2^i}\otimes \xi _i \Bigr)
\end{array}\] でもあります。これを見比べればよいです。
キリがいいので、この記事はこのあたりで終わりにします。次の記事では、\( A^{*,*}\) の環構造から \( A_{*,*}\) の余積が誘導されることを説明します。\( A^{*,*}\) に左右ふたつの \( H^{*,*}\)-構造があるので若干ややこしい面がありますが、基本的には (適切に左・右を見極めながら) 双対をとればいいという話になっている (はず) です。